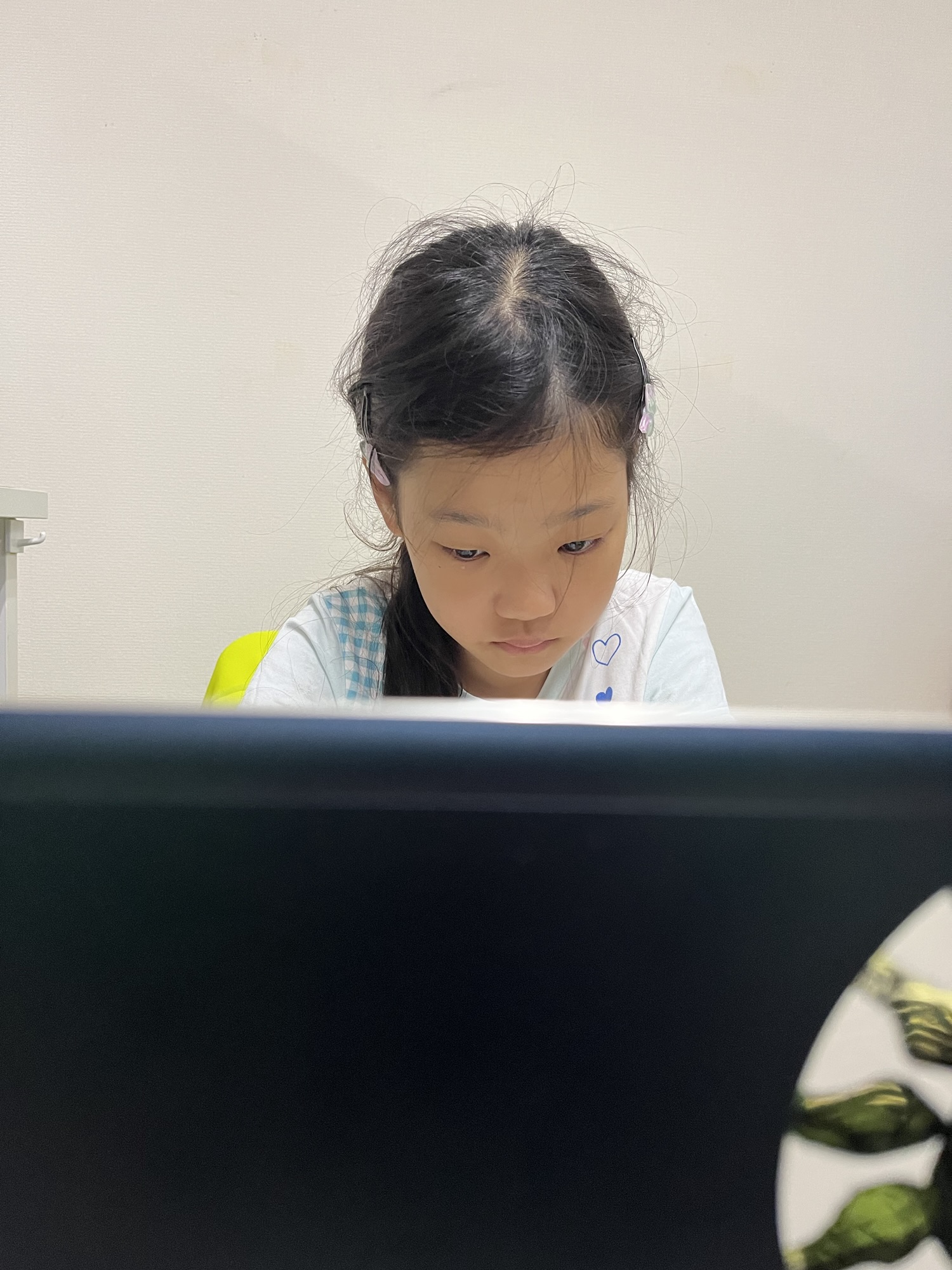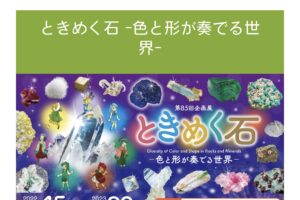半年間にわたる課外活動も 昨日のオンライン発表でようやっと終わりを迎えた。
グローバルの選出がまだだから 万が一 グローバルの方で選ばれたらまだプロジェクトは続くけど、日本の決勝10チームに選ばれていない段階でグローバルで残る可能性はないようにおもう。
去年に引き続き
号泣していた。
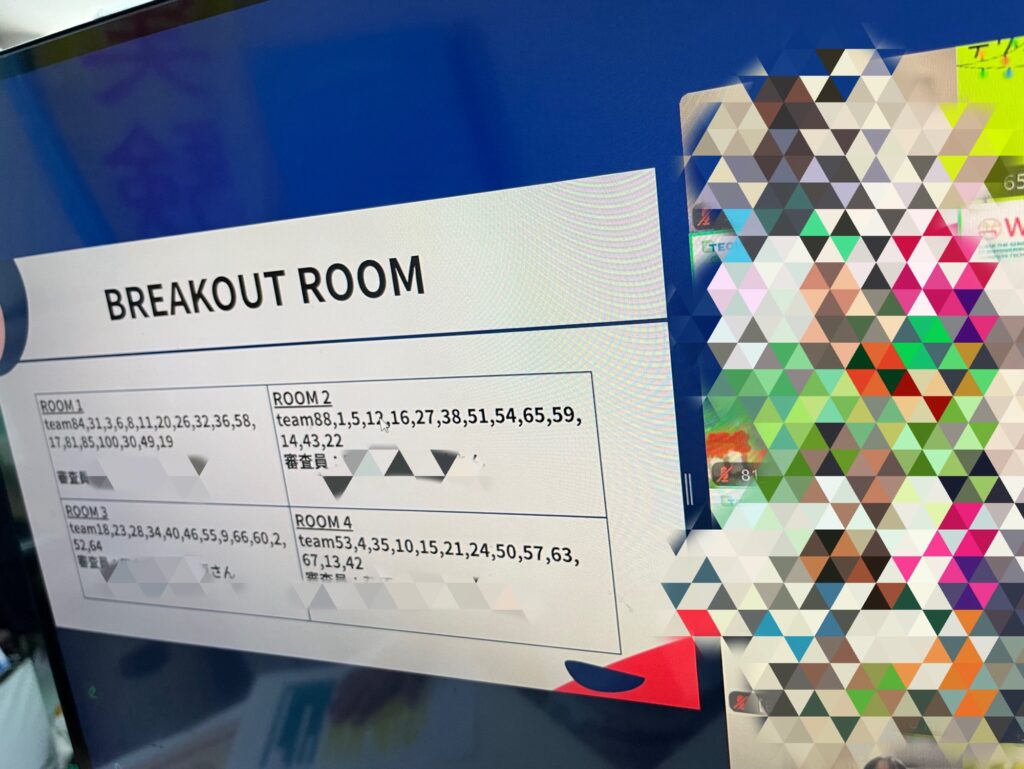
最後 発表まで続いたチームは
ぱっとみ40〜50チームくらいかな。
ぼくは 一切 昨日の発表や講評は聞いていないから
どのカテゴリーで何チームの参加があったかはわからない。
チーム5名でアプリをつくって
その過程をプレゼンで競うんだけど
これがまた アンケート調査 途中の社会人のメンターさんたちのレビュー 収支の予測なんかが入って
かなり ちゃんとしたものづくりコンテストになっている。
少なくとも高校大学のときのぼくなら半年の間に投げ出してる。
アプリ作成の時点で難易度が高い気がするんだけど
それをオンラインでチームを組んで
ビジネスモデルも相談して形をつくっていって
で
英語で各種発表までこぎつける っていうんだから
やっぱり難しいとおもう。
今回は すずのき的に
高校受験もかなり忙しかったし
春先も忙しかったし
そもそも
プログラミングももはやむすめのお荷物にしかならないし
何より
去年とちがって むすめは高校生(海外大に進む当時高3)と中学生たちと組めたから
ぼくは まったく ミーティングも一切聞かず
ほっといていた。
去年は小学生たちと組んだけど、全員早々にプロジェクトを離脱したから むすめの独りチームをメンターさんたちと共に手伝った。
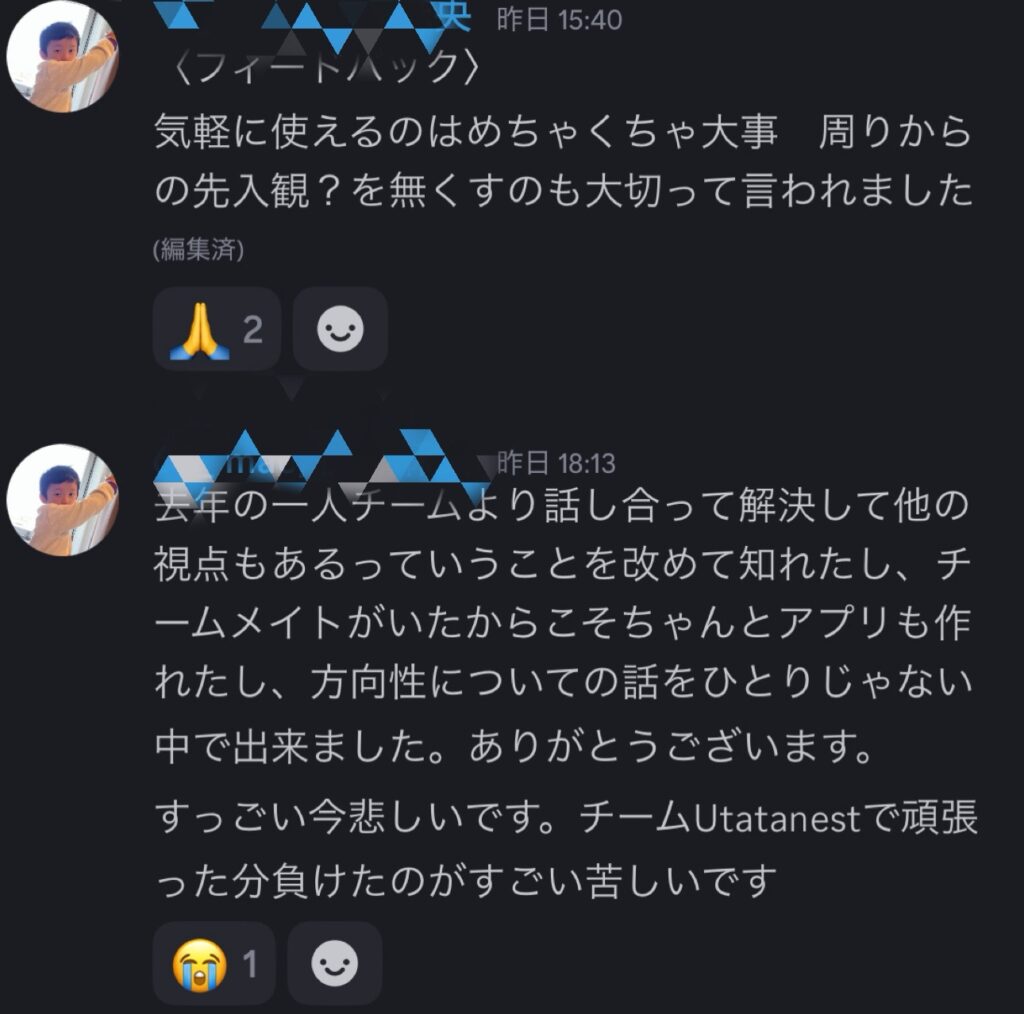
違う学齢の子たちと引っ張りあいながら進めていく という過程
優秀な人たちでも プロジェクトへのコミットはまちまちだっていう事実(半年間で5人中3人とんだ)
最後までベストを尽くしきる千葉からは遠くに住むど根性のスーパー中学生の存在(むすめから聞く限り考えられないくらい優秀だった)
AIの進化が たった一年でとんでもないことになってる事実
コーディングは 結局むすめがチャットgptと孤独にやりきってたのもあって
今回の半年も
学校では得ることができないことに触れられたように想像してる。
どうチームを動かしていくか
どうAIを動かしていくか
どうプロジェクトを転がしていくか
そういうのは実際に体験して感じることが多いわけだけど
就職する前に
やりようによっては
ずいぶんと経験できるもんなんだな なんておもってる。
むすめの場合 あと5年分は中学生以下のディビジョンで参加できる。社会人ボランティアのメンターさんたちにたっぷり指導してもらえるのもすごいことだとおもう。(去年はMicrosoftの女性エンジニア2名がむすめのチームのメンターさんたちだったんだけど、週に2時間はもらってたんじゃないかな)
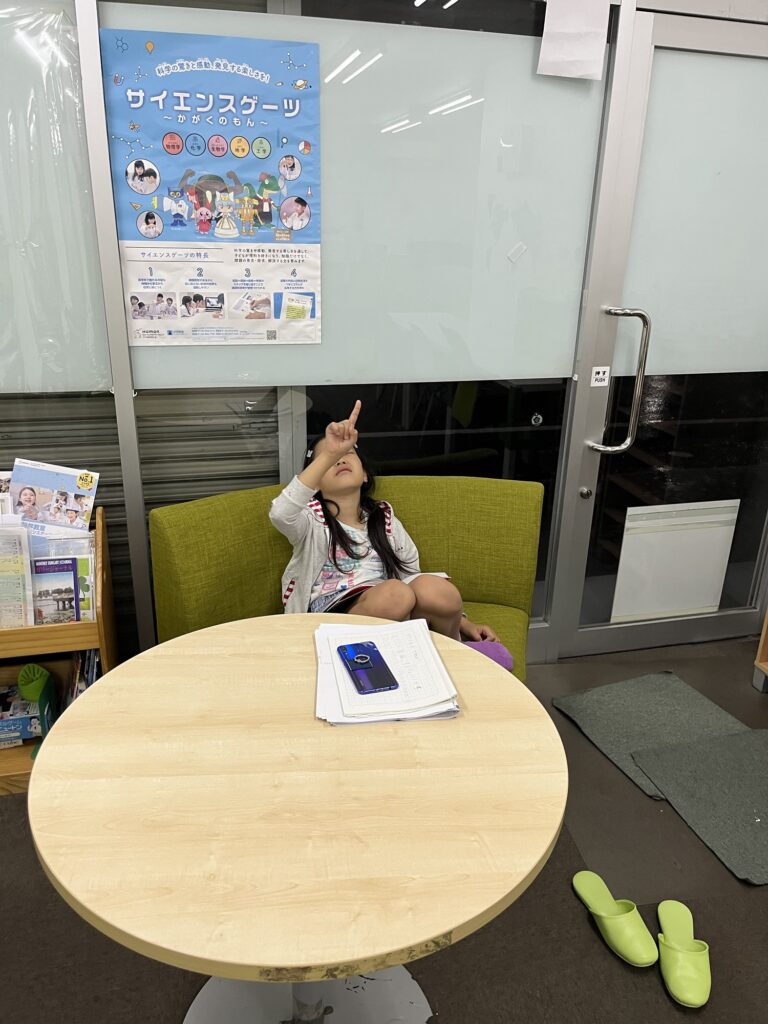
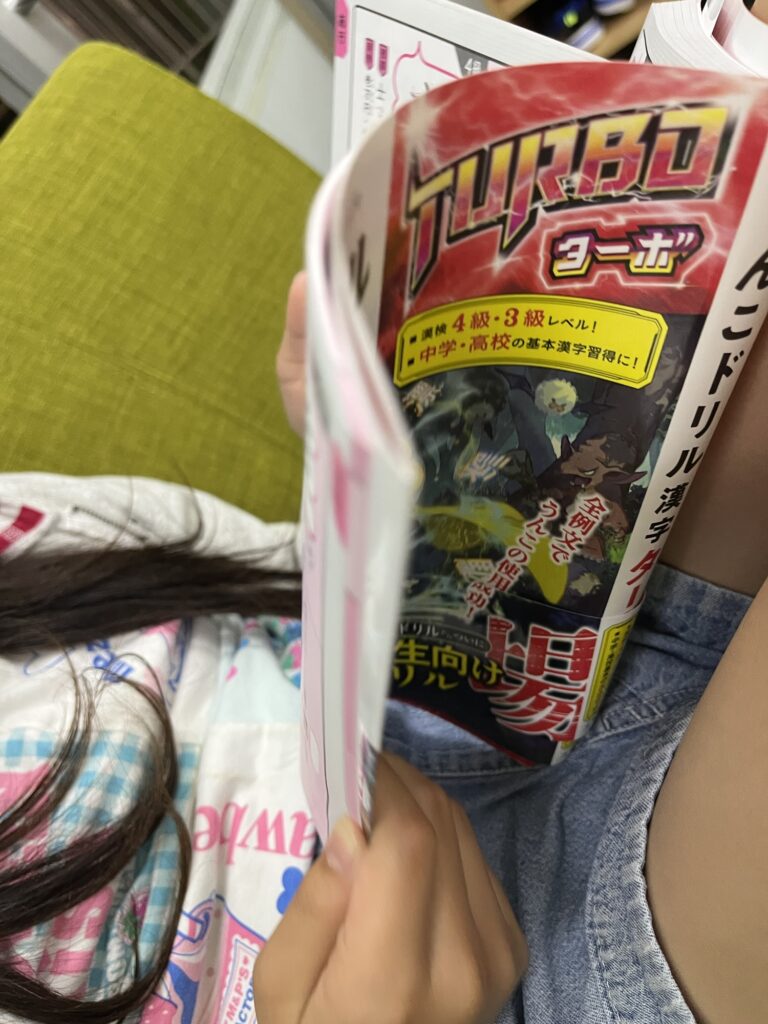
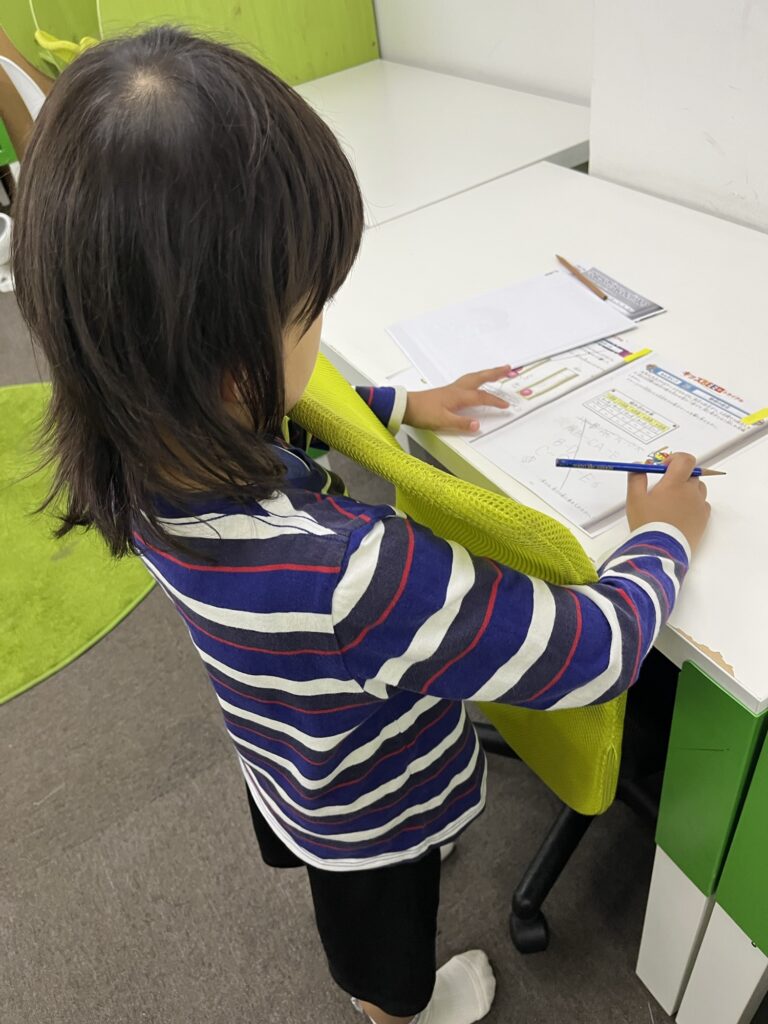
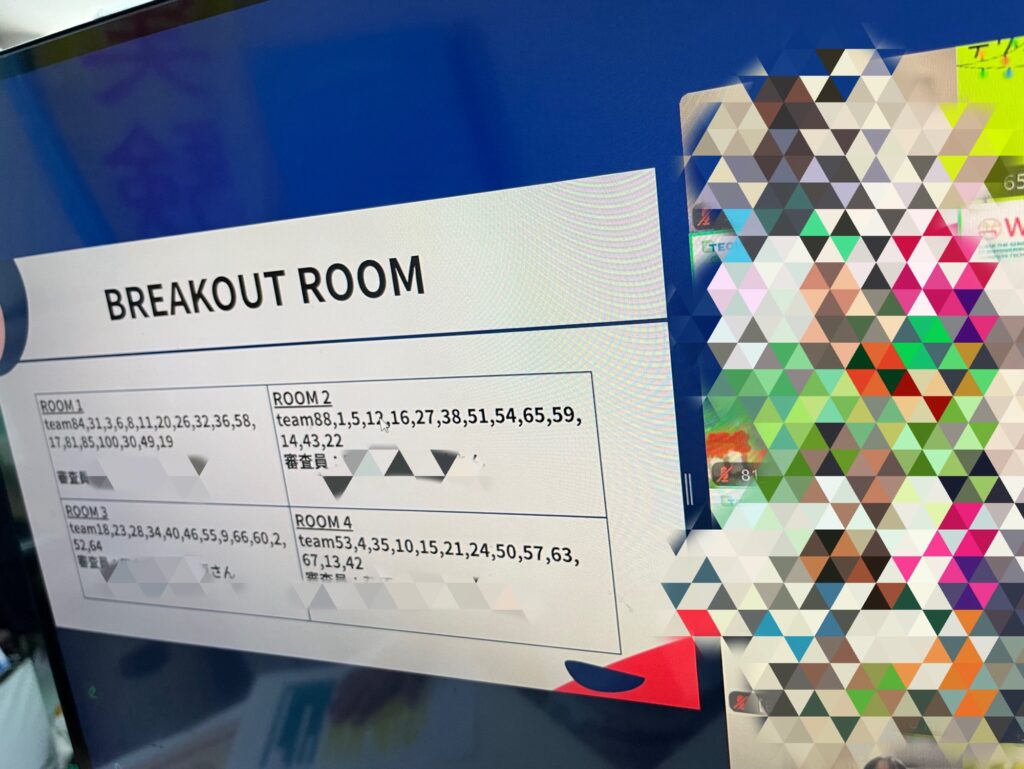
カリキュラムが自在な塾 すずのき
昨日夕方 バスケの合間に勉強しに来た小学4年生は
地理とアートを混ぜた課題を進めてる。
「いやいや この部分は削ってこいよ やすりかな?何とかしな。ここは茶っこく塗ったほうがよくない??? 次はどこの県にするよ? ふーん 埼玉は千葉のライバルだかんな」
みたいな やりとりをしながら進めてる。
サイエンスゲーツもそうだけどさ

学力向上の片手間で
学校ではできない学びを
手に届く範囲の子たちにわたしていけたら最高だよね
信じられないほどの勉強
の片手間で ね。